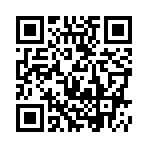2014年03月31日
『ウォルト・ディズニーの約束』
以下の文章では、映画『ウォルト・ディズニーの約束』の内容に触れています。ご了承ください。
『メリー・ポピンズ』の原作者P・L・トラヴァース。長年その映画化を望んできたウォルト・ディズニーに、やっと会うことにする……
この映画はディズニー・プロダクションが作っているので楽曲や映画の一部分は使えるし、ディズニーのキャラクターやディズニーランドを映し出しても問題はない。
実際のP・L・トラヴァースは当時、今のエマ・トンプソンよりもっと年上だったのではないかと思うが、やっぱりこれはエマの役だろう。パキパキのイギリス英語を話し、周囲の者をファーストネームで呼び、自分のことも「ウォルト」と呼ばせているディズニーに「ミセス・トラヴァースと呼んで欲しい」と言い、映画化に際して守ってほしいこと、してほしくないことを押し通そうとする。対するディズニーを演じるのは、トム・ハンクス。
P・L・トラヴァースについてはほとんど知らなかったので、描かれていく彼女の幼い頃が興味深かった。いかにもイギリス人の顔をしているが、実はオーストラリアの出身。酒のせいで仕事に支障が出るような、しかし娘の想像力だけは限りなく認めてくれた(というより彼自身がたぶん、空想の中に生きるのが好きな男だった)父親がいた……
トラヴァースの父は娘には甘かったが、父のせいで一家の生活が脅かされたことも確か。
一方、ディズニーには厳しい父、兄と自分に新聞配達をさせた父の思い出があった。
最初に考えられていた映画『メリー・ポピンズ』のラストシーンがどんなものだったかは知らないが、そこに出てくる幼い姉弟の父バンクス氏が良い人だとはっきりわかるようなラストにすることでトラヴァースは合意し、映画化もやっと軌道に乗り始める……
いろいろあって映画のプレミアの日を迎えても一筋縄ではいかない彼女、映画を見て涙を流しながらもディズニーから「大丈夫」とささやかれると、「アニメがひどくて」と答える。
トラヴァースにとってはこの映画化でもまだ不満があったのかもしれないが、一般的に考えれば、この映画があったからこそ『メリー・ポピンズ』はさらに有名になり、残ったのだと言える。そもそも映画『メリー・ポピンズ』が有名でなければ、その誕生秘話を描いたこの映画への興味もわかなかっただろう。あの映画があったからこそ『メリー・ポピンズ』は残り、こんな裏話も映画化される。
そう考えれば、トラヴァースをもてなし、手こずり、ロンドンへ訪ねてまで説得したディズニーはやはり仕事の出来る男だったのであり、はるか先を見通していたのだとも言えるだろう。
『メリー・ポピンズ』の原作者P・L・トラヴァース。長年その映画化を望んできたウォルト・ディズニーに、やっと会うことにする……
この映画はディズニー・プロダクションが作っているので楽曲や映画の一部分は使えるし、ディズニーのキャラクターやディズニーランドを映し出しても問題はない。
実際のP・L・トラヴァースは当時、今のエマ・トンプソンよりもっと年上だったのではないかと思うが、やっぱりこれはエマの役だろう。パキパキのイギリス英語を話し、周囲の者をファーストネームで呼び、自分のことも「ウォルト」と呼ばせているディズニーに「ミセス・トラヴァースと呼んで欲しい」と言い、映画化に際して守ってほしいこと、してほしくないことを押し通そうとする。対するディズニーを演じるのは、トム・ハンクス。
P・L・トラヴァースについてはほとんど知らなかったので、描かれていく彼女の幼い頃が興味深かった。いかにもイギリス人の顔をしているが、実はオーストラリアの出身。酒のせいで仕事に支障が出るような、しかし娘の想像力だけは限りなく認めてくれた(というより彼自身がたぶん、空想の中に生きるのが好きな男だった)父親がいた……
トラヴァースの父は娘には甘かったが、父のせいで一家の生活が脅かされたことも確か。
一方、ディズニーには厳しい父、兄と自分に新聞配達をさせた父の思い出があった。
最初に考えられていた映画『メリー・ポピンズ』のラストシーンがどんなものだったかは知らないが、そこに出てくる幼い姉弟の父バンクス氏が良い人だとはっきりわかるようなラストにすることでトラヴァースは合意し、映画化もやっと軌道に乗り始める……
いろいろあって映画のプレミアの日を迎えても一筋縄ではいかない彼女、映画を見て涙を流しながらもディズニーから「大丈夫」とささやかれると、「アニメがひどくて」と答える。
トラヴァースにとってはこの映画化でもまだ不満があったのかもしれないが、一般的に考えれば、この映画があったからこそ『メリー・ポピンズ』はさらに有名になり、残ったのだと言える。そもそも映画『メリー・ポピンズ』が有名でなければ、その誕生秘話を描いたこの映画への興味もわかなかっただろう。あの映画があったからこそ『メリー・ポピンズ』は残り、こんな裏話も映画化される。
そう考えれば、トラヴァースをもてなし、手こずり、ロンドンへ訪ねてまで説得したディズニーはやはり仕事の出来る男だったのであり、はるか先を見通していたのだとも言えるだろう。
2014年03月28日
本『この人の閾』を読んで
以下の文章では単行本『この人の閾』に収められた4篇の内容に触れています。ご了承ください。
表題作はずいぶん前に読んだことがある気もするのだが、あらためて、この本に入っているものと合わせて4作を読んだ。ストーリーを追うような話ではないから、そこに描かれる捉え方、感じ方について「ふむふむ、なるほど」と思えるところのある人には面白いということになるだろう。そういう意味で、私には面白かった。
たとえば『東京画』の中で、主人公が、周囲の建物が「うらぶれている」ことを説明しようとするのに、「建物が密集している」ことや「家の建材が粗末なトタン板であったりする」ことを挙げていたのに「縁の下がない」ことに気づいた時、漠然と「うらぶれている」と感じたものの正体を知った、と思うところ。なるほど「縁の下がない」というのは「うらぶれた」感じにつながるようだと納得した。
あるいは「自然教育園」の中を二人で歩く『夏の終わりの林の中』。古代の武蔵野の原始林からずっと続く林だと言うのだが、その中を歩きながら「人間の手がまるで全然入っていないかのように、手を入れている」のではないかと感じる感覚。
『夢のあと』では、今見てきた風景を夢のあとみたいだった、と言うと「なんかさあ、『夢のあとみたい』とか言っちゃうと、それで、何か言ったような気になっちゃうけどさあ。でも、本当はそういうのって、何も言ってないのと同じじゃない」と言われてしまう。
『東京画』には周囲の古い家が変わったり壊されていったりする描写があり、『夏の終わりの林の中』は変化していく林の中が舞台、『夢のあと』は、昔そこで遊んだりした場所を案内してもらう話。『この人の閾』も含め、「思い出」が重なってくるような箇所が必ずあるのだが、その、あるようなないような、かつては確かにあったが今は形が変わってしまったような、でもなくなりはしてもそれは単にそういうことである、というような感じが共通している。
だから『この人の閾』に出てくる主婦の真紀さんが本を読むことについて「だって、もう読むだけでいいじゃない。何読んだって感想文やレポートを書くわけじゃないんだし。読み終わっても何も考えたりしないでいいっていうのは、すごい楽なのよね」と言う時、それはそういう立場が羨ましいからそう書いているというよりも、あるようなないような、何かがあったとしてもたちまち曖昧になってりまうような感じを体現する立場として主婦を捉えている、ということなのかな、と思った。
表題作はずいぶん前に読んだことがある気もするのだが、あらためて、この本に入っているものと合わせて4作を読んだ。ストーリーを追うような話ではないから、そこに描かれる捉え方、感じ方について「ふむふむ、なるほど」と思えるところのある人には面白いということになるだろう。そういう意味で、私には面白かった。
たとえば『東京画』の中で、主人公が、周囲の建物が「うらぶれている」ことを説明しようとするのに、「建物が密集している」ことや「家の建材が粗末なトタン板であったりする」ことを挙げていたのに「縁の下がない」ことに気づいた時、漠然と「うらぶれている」と感じたものの正体を知った、と思うところ。なるほど「縁の下がない」というのは「うらぶれた」感じにつながるようだと納得した。
あるいは「自然教育園」の中を二人で歩く『夏の終わりの林の中』。古代の武蔵野の原始林からずっと続く林だと言うのだが、その中を歩きながら「人間の手がまるで全然入っていないかのように、手を入れている」のではないかと感じる感覚。
『夢のあと』では、今見てきた風景を夢のあとみたいだった、と言うと「なんかさあ、『夢のあとみたい』とか言っちゃうと、それで、何か言ったような気になっちゃうけどさあ。でも、本当はそういうのって、何も言ってないのと同じじゃない」と言われてしまう。
『東京画』には周囲の古い家が変わったり壊されていったりする描写があり、『夏の終わりの林の中』は変化していく林の中が舞台、『夢のあと』は、昔そこで遊んだりした場所を案内してもらう話。『この人の閾』も含め、「思い出」が重なってくるような箇所が必ずあるのだが、その、あるようなないような、かつては確かにあったが今は形が変わってしまったような、でもなくなりはしてもそれは単にそういうことである、というような感じが共通している。
だから『この人の閾』に出てくる主婦の真紀さんが本を読むことについて「だって、もう読むだけでいいじゃない。何読んだって感想文やレポートを書くわけじゃないんだし。読み終わっても何も考えたりしないでいいっていうのは、すごい楽なのよね」と言う時、それはそういう立場が羨ましいからそう書いているというよりも、あるようなないような、何かがあったとしてもたちまち曖昧になってりまうような感じを体現する立場として主婦を捉えている、ということなのかな、と思った。
2014年03月24日
『あなたを抱きしめる日まで』を見て
以下の文章では、映画『あなたを抱きしめる日まで』の内容・結末に触れています。ご了承ください。
原題はシンプルに『フィロミナ』。主人公の名前だ。事実をもとにした話。
十代で妊娠・出産し、修道院で働かされたフィロミナ。息子は三歳でアメリカへ養子に。それから数十年、今は五十歳になっているはずの息子に会いたいと、娘のジェーンに打ち明ける。ジェーンは、BBCの政府の広報担当をクビになった元ジャーナリストのマーティンに話をし、マーティンは記事にする約束で息子探しを手伝う。
アメリカまで行ったものの、息子は既に死んでいた。ゲイで、エイズによる死。しかし、弁護士として成功し、恋人もいたことがわかる。
ロマンス小説を好むおばさんで、アメリカの高級ホテルの朝食に浮き浮きするフィロミナ。そんなフィロミナへの同情よりも、修道院の非人道的なやり方への怒りが勝っているようなマーティン。日本のドラマだったら、この二人が心を通わせていく過程をもっとじっくり描きそうなものだが、あくまでも明らかになっていく事実の驚きで見せていく。
同性愛者へのバッシングの中で息子の晩年は大変ではなかったかと思わせるセリフもあるが、そこにはそんなにこだわらない。
マーティンが実は十年前に、フィロミナの息子に会ったことがあると思い出すシーンも短く描かれる。
「力強い握手だった。そう、力強い握手でなければ、あんな出世はしない」
会っていなくても言えるような感想である。しかしフィロミナは、それに満足そうな笑みを返す。
息子の墓は、かつてフィロミナが居た修道院の庭にあった。そこを訪れた二人は、母と息子がそれぞれこの修道院に問合せをしていたのに、修道院は二人を会わせなかったのだと知る。
マーティンは怒るが、双方に隠していた老尼僧に対して、フィロミナは「私はあなたを赦すわ」と言う。マーティンは「赦さない」と言う。
神を信じないと公言するマーティンに対して、フィロミナのこの「赦す」は宗教的なものなのか。「赦す」側が上位に立つのだとしたら、フィロミナはこの時、自分を苦しめてきた尼僧の上に立ったのか。
しかし映画は、そういう判断をしない。十代の妊娠や、国外への養子(しかも金銭のやり取りを伴う)という社会的な問題を含みながら、それがメインではない。事実が明らかになっていく面白さはまさにエンターテインメントだ。旅を終えたフィロミナとマーティンが友人になりました、という人情話でもない。
あらためて、ああ、スティーヴン・フリアーズ監督作品だなと思う。ずいぶん前の『マイ・ビューティフル・ランドレット』にしても、話題になった『クィーン』にしても、社会派的な側面はありつつ、見ている間のわくわく感が良かったのだ。そういう彼のサービス精神が、この映画にも生きている。
原題はシンプルに『フィロミナ』。主人公の名前だ。事実をもとにした話。
十代で妊娠・出産し、修道院で働かされたフィロミナ。息子は三歳でアメリカへ養子に。それから数十年、今は五十歳になっているはずの息子に会いたいと、娘のジェーンに打ち明ける。ジェーンは、BBCの政府の広報担当をクビになった元ジャーナリストのマーティンに話をし、マーティンは記事にする約束で息子探しを手伝う。
アメリカまで行ったものの、息子は既に死んでいた。ゲイで、エイズによる死。しかし、弁護士として成功し、恋人もいたことがわかる。
ロマンス小説を好むおばさんで、アメリカの高級ホテルの朝食に浮き浮きするフィロミナ。そんなフィロミナへの同情よりも、修道院の非人道的なやり方への怒りが勝っているようなマーティン。日本のドラマだったら、この二人が心を通わせていく過程をもっとじっくり描きそうなものだが、あくまでも明らかになっていく事実の驚きで見せていく。
同性愛者へのバッシングの中で息子の晩年は大変ではなかったかと思わせるセリフもあるが、そこにはそんなにこだわらない。
マーティンが実は十年前に、フィロミナの息子に会ったことがあると思い出すシーンも短く描かれる。
「力強い握手だった。そう、力強い握手でなければ、あんな出世はしない」
会っていなくても言えるような感想である。しかしフィロミナは、それに満足そうな笑みを返す。
息子の墓は、かつてフィロミナが居た修道院の庭にあった。そこを訪れた二人は、母と息子がそれぞれこの修道院に問合せをしていたのに、修道院は二人を会わせなかったのだと知る。
マーティンは怒るが、双方に隠していた老尼僧に対して、フィロミナは「私はあなたを赦すわ」と言う。マーティンは「赦さない」と言う。
神を信じないと公言するマーティンに対して、フィロミナのこの「赦す」は宗教的なものなのか。「赦す」側が上位に立つのだとしたら、フィロミナはこの時、自分を苦しめてきた尼僧の上に立ったのか。
しかし映画は、そういう判断をしない。十代の妊娠や、国外への養子(しかも金銭のやり取りを伴う)という社会的な問題を含みながら、それがメインではない。事実が明らかになっていく面白さはまさにエンターテインメントだ。旅を終えたフィロミナとマーティンが友人になりました、という人情話でもない。
あらためて、ああ、スティーヴン・フリアーズ監督作品だなと思う。ずいぶん前の『マイ・ビューティフル・ランドレット』にしても、話題になった『クィーン』にしても、社会派的な側面はありつつ、見ている間のわくわく感が良かったのだ。そういう彼のサービス精神が、この映画にも生きている。
2014年03月18日
『私の嫌いな探偵』感想②
後半(5話~8話)の見どころは、朱美×鵜飼×流平、あるいは朱美×鵜飼×砂川のやりとりがこなれてきて面白かったところ。テンポというかタイミングというか、ちょっとした動作の合わせ方とか。
進展したことは最終話に至ってまさかの「鵜飼は朱美のことが好き?」というのがあったが、これを恋愛感情というのなら、そういう感情は特に入れなくてもよかったのに、と思う。推理マニアという一点だけで結びついているだけで十分なのでは?
私は、玉木宏は感情を抑える(ような立場に立たされる)役が似合うと思うし、それが抑えきれずにあふれ出す表現もまた素晴らしいと思うのだが、その感情が「恋愛」である場合はよほど相手に魅力がないと説得力がない。酒屋のさやかさんを「小娘」呼ばわりしていた鵜飼から見れば、女子大生の大家さんは小娘すぎて恋愛の対象ではないと思うけどなぁ…
まあ、この脚本自体、じっくり一歩一歩展開していくというよりは、急展開だったり、反復していくうちに様々なバリエーションが出てきたりすることの多いものだったと思うので、急展開自体は驚くことではないのかもしれないが、恋愛要素は不要だったのでは?
殺人の理由は聞かないのが鵜飼の主義だが、7件の事件のうち、1件は事故隠しなので除くと、5件がある人を愛するゆえの殺人、と言える。そして最終話も「愛による殺人」と言ってもいいのだが、他の対象が人だったのに対し、ここでは愛の対象が烏賊川市。 登場人物達の住む市である。
最近の、なんとなく愛国的であることが流行しているような雰囲気の中で、自分の住む市に対するすさまじい愛を持った男が殺人を犯すというのはかすかな皮肉? とも思ったが、まあこのドラマの場合、あまりそういう詮索はしないほうがよいのだろう。
進展したことは最終話に至ってまさかの「鵜飼は朱美のことが好き?」というのがあったが、これを恋愛感情というのなら、そういう感情は特に入れなくてもよかったのに、と思う。推理マニアという一点だけで結びついているだけで十分なのでは?
私は、玉木宏は感情を抑える(ような立場に立たされる)役が似合うと思うし、それが抑えきれずにあふれ出す表現もまた素晴らしいと思うのだが、その感情が「恋愛」である場合はよほど相手に魅力がないと説得力がない。酒屋のさやかさんを「小娘」呼ばわりしていた鵜飼から見れば、女子大生の大家さんは小娘すぎて恋愛の対象ではないと思うけどなぁ…
まあ、この脚本自体、じっくり一歩一歩展開していくというよりは、急展開だったり、反復していくうちに様々なバリエーションが出てきたりすることの多いものだったと思うので、急展開自体は驚くことではないのかもしれないが、恋愛要素は不要だったのでは?
殺人の理由は聞かないのが鵜飼の主義だが、7件の事件のうち、1件は事故隠しなので除くと、5件がある人を愛するゆえの殺人、と言える。そして最終話も「愛による殺人」と言ってもいいのだが、他の対象が人だったのに対し、ここでは愛の対象が烏賊川市。 登場人物達の住む市である。
最近の、なんとなく愛国的であることが流行しているような雰囲気の中で、自分の住む市に対するすさまじい愛を持った男が殺人を犯すというのはかすかな皮肉? とも思ったが、まあこのドラマの場合、あまりそういう詮索はしないほうがよいのだろう。
2014年03月15日
『桐島、部活やめるってよ』
原作は読んでいないのだが、映画もかなり評判になったものだったので、放映された機会に見た。
以下の文章では映画『桐島、部活やめるってよ』の内容に触れています。ご了承ください。
バレーボール部のエースなのに突然部活をやめると言い、学校へも来なくなった桐島。不在の桐島をめぐって、バレー部の男子、桐島とつき合っていた女子とその友達、桐島の友人だった男子グループ……と、さまざまな立場からの数日間が描かれる。出演している若手俳優たちは神木隆之介、橋本愛、東出昌大…となかなかのメンバー。
一見して感じるのは「テンションの低さ」だ。最近、テンションの高いTVドラマを見ていたからそう感じるのかもしれないけれど、桐島と連絡もとれない状態になって苛立ち焦りながらも、誰も声を荒らげたり叫んだりすることはない。奇妙なクライマックスは、桐島が屋上にいると思った男子たちが、屋上で撮影中の映画部員たちの中へ走り込み、言い争いになる場面だが、それだって高校生を主人公にした映画ならなりがちなように殴り合いになるわけではない。そういう醒めた感じがこの映画の興味深いところで、びっくりマーク付きの「感動!」なんてものを求める人は、この映画を見てもつまらないだろう。
高校生の部活にもカッコイイものとカッコ悪いものとがあって、どうやら映画部は最もカッコ悪い部類に入るらしい。この映画の監督の吉田大八監督は「学校がすべてじゃない」と思いながらもそれを押し付けるのではなく「高校生にとっては、やっぱり学校がすべてなんですよね」と言っている。だから学校外の映画館で日曜日にかすみ(橋本愛)と出会い、ちょっといい気分になった映画部の涼也(神木隆之介)は、学校という場所に戻ればたちまち自分はかすみの相手になんかなれないという事実を突きつけられるのだ。
それにしたって映画の作り手たちが映画部の涼也に自分の思いを重ねるのは当然のことだろうし、顧問の先生の脚本ではなく自分で書いた脚本で映画を撮ろうとする涼也は、実は一番よくものごとが見えているようでもある。その脚本の中のセリフとして「戦おう。ここがおれたちの世界だ。おれたちはこの世界で生きていかなければならないのだから」という言葉も出てくる。また、父親譲りの古い8ミリカメラで撮影して「フィルムにはビデオに出せない味がある」と主張する涼也には共感する映画ファンも多いかもしれない。
その上、涼也は自分がどの程度の者かもわかっているのだ。桐島の親友でスポーツ万能、彼女もちゃんといる宏樹(東出昌大)に「将来は映画監督?」と聞かれると、それはない、無理、と答える。このテンションの低さと悟りっぷりと「それでも好きなことは続ける」というのがまさに今の気分、と言われれば確かにそんな気がする。
以下の文章では映画『桐島、部活やめるってよ』の内容に触れています。ご了承ください。
バレーボール部のエースなのに突然部活をやめると言い、学校へも来なくなった桐島。不在の桐島をめぐって、バレー部の男子、桐島とつき合っていた女子とその友達、桐島の友人だった男子グループ……と、さまざまな立場からの数日間が描かれる。出演している若手俳優たちは神木隆之介、橋本愛、東出昌大…となかなかのメンバー。
一見して感じるのは「テンションの低さ」だ。最近、テンションの高いTVドラマを見ていたからそう感じるのかもしれないけれど、桐島と連絡もとれない状態になって苛立ち焦りながらも、誰も声を荒らげたり叫んだりすることはない。奇妙なクライマックスは、桐島が屋上にいると思った男子たちが、屋上で撮影中の映画部員たちの中へ走り込み、言い争いになる場面だが、それだって高校生を主人公にした映画ならなりがちなように殴り合いになるわけではない。そういう醒めた感じがこの映画の興味深いところで、びっくりマーク付きの「感動!」なんてものを求める人は、この映画を見てもつまらないだろう。
高校生の部活にもカッコイイものとカッコ悪いものとがあって、どうやら映画部は最もカッコ悪い部類に入るらしい。この映画の監督の吉田大八監督は「学校がすべてじゃない」と思いながらもそれを押し付けるのではなく「高校生にとっては、やっぱり学校がすべてなんですよね」と言っている。だから学校外の映画館で日曜日にかすみ(橋本愛)と出会い、ちょっといい気分になった映画部の涼也(神木隆之介)は、学校という場所に戻ればたちまち自分はかすみの相手になんかなれないという事実を突きつけられるのだ。
それにしたって映画の作り手たちが映画部の涼也に自分の思いを重ねるのは当然のことだろうし、顧問の先生の脚本ではなく自分で書いた脚本で映画を撮ろうとする涼也は、実は一番よくものごとが見えているようでもある。その脚本の中のセリフとして「戦おう。ここがおれたちの世界だ。おれたちはこの世界で生きていかなければならないのだから」という言葉も出てくる。また、父親譲りの古い8ミリカメラで撮影して「フィルムにはビデオに出せない味がある」と主張する涼也には共感する映画ファンも多いかもしれない。
その上、涼也は自分がどの程度の者かもわかっているのだ。桐島の親友でスポーツ万能、彼女もちゃんといる宏樹(東出昌大)に「将来は映画監督?」と聞かれると、それはない、無理、と答える。このテンションの低さと悟りっぷりと「それでも好きなことは続ける」というのがまさに今の気分、と言われれば確かにそんな気がする。
2014年03月01日
『マイ バック ページ』
以下の文章では、映画『マイ・バック・ページ』の内容に触れています。ご了承ください。
見終わって、もやもやした。私はこれを日本映画専門チャンネルの「日曜邦画劇場」で見たので、前後に解説というか感想が付いている。その中の「梅山に対する沢田の共感と幻滅、そしてクライマックスの涙は、当時の若者たちの学生運動に対するナイーヴな期待と挫折感を残酷なほどに描き出していたように思います」という言葉で言い尽くされているような気もする。もっと痛烈に「ジャーナリストというのは、この程度のものだ。自分と感性が似ている(ように見える)人間なら信じてしまうのだ」と見た人もいるようだ。
実話に基づいていて、背景となる時代は1969年~1972年。主人公の雑誌記者・沢田は学生運動を取材するうちに知り合った―というよりむしろ向こうから近づいてきた梅山に何度か会い、独占スクープを取ろうとする。梅山たちが実行したのは自衛隊基地から武器を盗み出すことだが、肝心の武器は入手できず、自衛隊員一人を殺す結果になる。沢田も罪に問われ、実刑判決を受ける。
梅山たちの「権力側はデモ隊に暴力をふるい、殺しさえする。こちらもまず武装すべきだ」という意見はもっともなようにも聞こえる。沢田もそれを全面的に信じていたわけではないだろうが、梅山に対して友情めいたものを感じていたように見える。沢田を演じる妻夫木聡がいかにも人がよさそうで、梅山を演じる松山ケンイチがうさんくさそうなのはイメージ通りの配役にも見え、そういう意味では冒険的ではない。
なぜ今、この話を映画にしたのかという疑問は残るのだが、私にとって印象的だったのは、沢田が表紙モデルの女の子と映画を見に行った後の場面だ。ジャック・ニコルソンが泣くところが好き、と言う女の子に対して沢田は「泣く男なんて男じゃないよ」と言うのだが、女の子は「きちんと泣ける男の人が好き」と言う。その意味では、これは沢田が「きちんと泣けるようになるまで」の話なのだ。そしてその泣き始め、泣いていく表情をじっくり映してもらえた妻夫木は、役者として恵まれていると言えるのだろう。
見終わって、もやもやした。私はこれを日本映画専門チャンネルの「日曜邦画劇場」で見たので、前後に解説というか感想が付いている。その中の「梅山に対する沢田の共感と幻滅、そしてクライマックスの涙は、当時の若者たちの学生運動に対するナイーヴな期待と挫折感を残酷なほどに描き出していたように思います」という言葉で言い尽くされているような気もする。もっと痛烈に「ジャーナリストというのは、この程度のものだ。自分と感性が似ている(ように見える)人間なら信じてしまうのだ」と見た人もいるようだ。
実話に基づいていて、背景となる時代は1969年~1972年。主人公の雑誌記者・沢田は学生運動を取材するうちに知り合った―というよりむしろ向こうから近づいてきた梅山に何度か会い、独占スクープを取ろうとする。梅山たちが実行したのは自衛隊基地から武器を盗み出すことだが、肝心の武器は入手できず、自衛隊員一人を殺す結果になる。沢田も罪に問われ、実刑判決を受ける。
梅山たちの「権力側はデモ隊に暴力をふるい、殺しさえする。こちらもまず武装すべきだ」という意見はもっともなようにも聞こえる。沢田もそれを全面的に信じていたわけではないだろうが、梅山に対して友情めいたものを感じていたように見える。沢田を演じる妻夫木聡がいかにも人がよさそうで、梅山を演じる松山ケンイチがうさんくさそうなのはイメージ通りの配役にも見え、そういう意味では冒険的ではない。
なぜ今、この話を映画にしたのかという疑問は残るのだが、私にとって印象的だったのは、沢田が表紙モデルの女の子と映画を見に行った後の場面だ。ジャック・ニコルソンが泣くところが好き、と言う女の子に対して沢田は「泣く男なんて男じゃないよ」と言うのだが、女の子は「きちんと泣ける男の人が好き」と言う。その意味では、これは沢田が「きちんと泣けるようになるまで」の話なのだ。そしてその泣き始め、泣いていく表情をじっくり映してもらえた妻夫木は、役者として恵まれていると言えるのだろう。